「将来的にはカウンセラーになろうと思っています」
時々私はこのようなお話を聞くことがあります。
カウンセリングの時、コーチングの時、個別レッスンの時、あるいはセミナーを開催している時などにです。
つまり、ゆくゆくはカウンセラーやそれに準ずるような仕事をしてみたい。
そのために傾聴やカウンセリングを勉強したいと思っている。
そういう目標をお持ちの方々だということです。
カウンセラーになるということ。
しかも、カウンセラーを生業にしようということ。
こうしたテーマでなかなかまとまって話をする機会がありません。
オンライン講座では、カウンセラーとしてやっていくための様々な情報は配信しています。
しかし、それ以外の機会では十分にお話をすることがありません。
ですので、今回はカウンセラーを生業としていくためにはどうすればいいのかについて書いてみたいと思います。
もくじ
辛い経験をした人の方がカウンセラーに向いている?
「辛い経験をした人の方が、人の援助がしっかりできるのか?」
一般的には同じ経験をしていないと、その人の痛みや気持ちはわからないと言われます。
しかし、果たして本当にそうなのでしょうか?
私は違うと思っています。
同じ経験をしていなくても、その人の痛みへの共感は可能です。
また、同じ経験をしていても、相手の気持ちがわかるとは限りません。
もし、同じ経験をしていないとわからないとなると、誰もカウンセラーにはなれないということになります。
カウンセラーになった人間が、全てのクライエントと同じ経験など出来ないからです。
私でいうなら、技術者の経験もないし、うつになったこともありません。
そうなると、私はどんなにトレーニングとカウンセリングの経験値を積んでも、技術者を援助できないし、うつの方の援助もできないということになります。
しかし実際には、カウンセラーは自分が経験したことがない問題でも、一緒に解決に取り組んだり共感することが可能です。
そしてこれは逆のこともいえるのです。
同じ経験をした人でも、相手の痛みや気持ちに共感できない場合もあるのです。
いえ、むしろ同じ経験をしているのに共感できない場合が圧倒的に多いでしょう。
うつを経験した人でも、うつを経験した人に寄り添えない。
同じ技術者の経験があるのに、他の技術者の苦悩に寄り添えない。
もし寄り添えると言うのなら、同じ職場の技術者同士でいつも共感し合えるはずですが・・・・
では、なぜ同じ経験をしていなくても共感できたり寄り添えるのでしょうか?
寄り添うためには寄り添うための力が要る
どうして同じ経験をしているはずなのに、共感や寄り添いが上手くできないのでしょうか?
その答えはこうです。
「寄り添うためには、寄り添えるための”力”が要る」
つまり、同じ経験をしているからとか、寄りといたいという思いが強いからとか、それだけでは本当の意味では寄り添えないということです。
寄り添うためには、寄り添うための力(専門性、スキル、経験値、姿勢など)が改めて必要になります。
ここのところを理解できていない方も多いのではないでしょうか?
例えば、思いだけで人を助けることができるのなら、愛ある親御さんは子供を助けられるということになります。
ところが実際は愛ある親御さんでも子どもを助けることができないケースがたくさんあります。
愛情もあり、どうにか助けたいと思っている親御さんでも、不登校のお子さんを立ち直らせることができないケースは数多あります。
同じ経験をしたからその人の痛みがわかる?
ある意味、これは危険な発想です。
同じ経験と書いていますが、厳密には同じ経験ではありません。
同じような(似たような)経験とは言えますが、同じではないのです。
不登校を経験しても、その問題や経験の世界は一人一人みな違います。
うつを経験したといっても、これも一人一人全て違います。
同じ技術者であっても、やはり一人一人みな違います。
一方、同じ経験をしていなくても共感し、寄り添うことができる。
例えばそれがカウンセラーなら、寄り添うための力をつけているから可能になります。
傾聴力、共感能力、応答能力、ケース全体を読み取る力、これらに関する専門性やスキル、経験値があるわけです。
だから、例えば私でいえば技術職に就いたことがないのに、技術者の方のカウンセリングができるわけです。
もちろん、技術者の技術に関する専門的な指導やコンサルティングはできません。
出来るのは心の問題、人間関係の問題、仕事の仕方、生き方等についてです。
自分が辛い経験をしたから、同じ(ような)経験をした人の役に立ちたい。
こういう思いは大切であることは間違いありません。
しかしこれを「同じ経験をしたから役に立てる」と安易に結びつけることは危険です。
心理カウンセラーになるには過去の経験は関係なく、十分なトレーニングこそ必要
先ず、同じ辛い経験をしたとして、その経験をきちんと克服できているのか?
うつならうつから完全に回復し、うつのきっかけとなった問題をきちんと解消できているのか?
そしてその上で専門的なことを学習し、必要なトレーニングを重ねてきたか?
こうしたところのチェックに、安易さや妥協が入り込む余地はありません。
わかりやすい例でいうと、お酒漬けになっている医師が、アルコール依存症の患者をきちんとケアできると思いますか?という話です。
時々うつになる人が、うつの人のカウンセリングができますか?というのと同じです。
だから私はカウンセラーを目指す人にはカウンセリングをしっかり受けて欲しいし、それ以上に十分なトレーニングを積んで欲しいのです。
カウンセラーになるためのカウンセリング(教育分析)は必須
まず、カウンセラーとしてカウンセリングをするのであれば、心が健康であることが絶対条件です。
ロジャーズが言う「十分に機能する人」であったり、マズローが言う「 自己実現的な人間」である必要があります。
心のバランスが良好で、安定していて、人間関係を築く上でも特に問題がない。
そういうパーソナリティがカウンセラーとしては必要条件だと考えます。
そのために、まずはカウンセリングを受けることをおすすめしています。
つまり、指導者からカウンセリングを受け、自分がカウンセラーとしてカウンセリングをする上で問題を抱えていないか。
心の状態が健康であるかなどをチェックしたり、問題があれば解決させていくわけです。
こういうカウンセリングを「教育分析」と呼びます。
カウンセラーを目指すのであればまず教育分析を受けましょう。
ただし、信頼できる指導者から受けることです。
「心が健康でなければカウンセリングをしてはだめなのですか?」
この質問に対する答えは「YES」 です。
これは当たり前の事なんですけどね。
心に問題がある人がカウンセリングしてはならないと私は思っています。
心が健康であるからこそ「健康な心とは何か」ということを実感でき、その感覚からも確かなカウンセリングをすることができるわけです。
カウンセラーになるためにカウンセリングを受けたくないというのは、スポーツ選手になりたいがトレーニングなんか嫌だと言っているようなものです。
心理カウンセラーとしての専門性と専門的なスキルを身につけることが重要
さらに、教育分析に加えてカウンセリングのスキルを身につける必要があります。
どういうトレーニングが有効かということについてはオンライン講座や
YouTube等でお話しているので、ここでは簡単に。
傾聴力、共感力、応答力、事例の検討力などをマスターしてください。
そのためにロールプレイ、逐語検討、エンカウンターグループ、応答訓練、事例検討、教育分析など。
様々な事例、様々なクライエント、様々な話に対応できる力を磨いてください。
精神医学の基礎的な知識も必要です。
クライエントに対して、必要な時に精神科や心療内科の受診を薦めるためにです。
あるいは、精神病に対するカウンセリングの留意点やポイントを理解するためです。
さて、ここまではカウンセリングそのもののお話でした。
次に、カウンセリングを生業にするために必要なことについて話します。
日本はカウンセラーが職業として成立していない(食べていけない)国
カウンセリングの資格を取ったら、即、食べられるようになると思ったら大間違いです。
病院や大学に所属したり、どこかのカウンセリング団体やスクールに所属しても、食べていけるほどの収入を得るには厳しい場合が多いです。
「所属」という形態で十分な収入を得るのであれば、複数の組織や団体に所属する必要が出てきます。
ただ、忙しくて負担の多い割には、それに見合った収入を得るのは難しいでしょう。
では、私のような個人事業主ではどうか。
複数の団体に所属するよりも多くの収入を得ることは可能ですが、一方でうまく出来なければ全く収入につながらないというリスクも大きいです。
つまり、カウンセラーとして食べていくというのは恐ろしく大変で難しいことだと言わざるを得ません。
私の場合個人事業主ではありますが、自分でセミナーを主催したり、カウンセリングを教えたり、企業の研修をしたりもしています。
生業にしていくためには様々なことを知らなければなりません。
あるいは様々なことができなくてはなりません。
個人事業主として、自分の事業を成立させるための知識や思考錯誤ですね。
マーケティングやビジネスモデルの組み立て、財務的なこと、経営のこと。
そういう様々な知識と実践ができなければ、個人事業主として、カウンセラーとして食べていけるようになるのは難しいでしょう。
私の見立てですが、カウンセラーを仕事にして食べていけている人は、全体の5%いるかいないかだと思います。
安易に考えてしまうと、手痛いめにあいます。
カウンセリングをするということ、そしてカウンセラーを生業にするということは、特にこの日本では恐ろしく難しいことなんです。
日本の職業の中では、芸術関係と同様に「正社員」という雇用形態がびっくりするくらい確立されていない職業です。
心理カウンセラーとしての開業(起業)は茨の道だが・・
この情報を聞いて「自信ややる気がなくなりそう」だとしたら、カウンセラーを目指すのはあきらめた方がいいでしょう。
「それでも可能性に賭けてみたい」という意志があるのであれば、後悔のないように挑戦してみたら良いと思います。
私も最少は師匠に「見通しが甘い」「食べていける世界じゃない」「無理だ」をかなり厳しく言われても全くひるむことなく突き進みました。
その位の気概、思いがなければ生業にはできないです。
しかし、何度も言いますが厳しい船出であり、困難の連続となる航路を行かねばなりません。
私が知っている方で、カウンセラーを生業とできた人たちも、そこにたどり着くまでは数多の苦労を重ねていました。
ただ、途中であきらめず、努力や試行錯誤を延々と続けたことで、現在は生業として安定した形で従事されています。
何事もそうですが、結果が出るまでいかに試行錯誤を続けられるかが大事です。
結果を出すには「結果が出るまで続けること」が一番の秘訣だからです。
でも、この努力をできる人が全体の5%だということになります。
心理カウンセラーになるには困難を困難と思わないメンタリティーが必要
私の場合、カウンセラーを目指そうと思ったとき、とにかく試行錯誤しようということしか考えていませんでした。
出来るかできないかなんて考えていなかったんです。
出来るかどうかで考えたら、やったことのないことだから、自信なんてありません。
出来るかできないかで考えてしまうから、みな、一歩を踏み出せないのです。
明らかに自分には無理だと思うのなら、あきらめるのも一つの選択肢。
でも、私のようにどんなに困難だと聞かされても臆する気持ちは微塵もなく、「困難ならどうその困難を克服できるか」と思える人なら挑戦すれば良いと思います。
私はカウンセラーとして起業するための準備中も、起業してからも、どうすれば上手くできるかということしか考えてきませんでした。
上手くやることだけに集中していたといえます。
他の余計なことには気持ちを奪われず、ひたすら「どうすればできるか」だけを考えてきました。
この経験自体が私のパーソナリティーをたくましくしてくれたかもしれません。
いずれにしても、カウンセリングを仕事にしたいと思っている方には、このあたりをよくよく調べ、検討して頂きたいと思います。
【動画】カウンセラーはカウンセリングを受けよう
最後にカウンセラーになるために最も重要なトレーニングの一つ、教育分析について短い動画にまとめてみました。
心理カウンセラーになりたい人は、ぜひご覧ください。
「臨床カウンセラー養成塾の無料メルマガ」でもっと読める!
こうした内容をもっと知りたいという方のために「臨床カウンセラー養成塾」のメルマガをお届けしています。あなたのスマホ、タブレット、PCに無料で読むことができます。ご購読をご希望される方は、下記からご登録頂けます。メールは「臨床カウンセラー養成塾」という件名で届きます。購読解除はメルマガの巻末(下部)より、いつでも出来ます。興味のある方はご購読ください。
追伸:
さらに、傾聴について、こうした皆が知らない真実を、今回一冊のレポート(56ページのPDF無料レポート)にまとめました。
無料PDFレポート「誤解されている傾聴スキル8つの真実」
~形だけの傾聴から、人と心通わす傾聴へ~
こういう話は、おそらく他では知り得ないと思います。
本当の意味で、現場で使える傾聴を身につけたい、そのために必要なことを知っておきたいという方。
下記からメルマガ登録すると無料PDFレポートもお読み頂けます。
【無料PDFレポート「誤解されている傾聴スキル8つの真実」】
↓ ↓ ↓ ↓
無料PDFレポート
【月額2980円のオンライン講座】
傾聴・カウンセリングや心理学、人生100年時代の幸せな生き方を学習できる「オンライン講座」が好評です。
会員限定サイトの動画セミナー、コラム記事が、スマホ・PC・タブレットから見放題でなんと月額2980円!













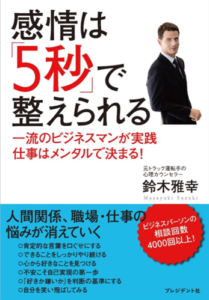
最近のコメント