カウンセリングの元祖ともいえるのは、カール・ロジャーズの「来談者中心療法」であり、その真骨頂の一つが「非指示的である」ということです。
そしてそこには「人間援助」の根本的なカギがあります。
今回はある学校の教師の授業、また別の引きこもり援助者の援助の仕方との比較もしながら、改めてカウンセリングや傾聴をカール・ロジャーズの来談者中心療法の観点から解説します。
もくじ
ある教師と引きこもり援助者とロジャーズとの共通点
最近、NHKのドキュメント番組で、教育者と心理援助者を続けて取り上げていました。
一人は、生徒が自主的に問題に取り組んでいく授業を展開する教師。
もう一人は引きこもりの支援を個人で行っている援助者でした。
番組を観ていて、この二人にはある共通点があるなと感じました。
それは、二人ともロジャーズの教育観、臨床観に基づいているということです。
おそらく、二人ともロジャーズの理論や実践を学んだわけではないでしょう。
たまたま、それぞれに行きついた形がロジャーズと同じだったということだと思います。
しかし、それぞれに注目すべき点がありました。
教師は数学を教えていて、進学校、補習塾、そして養護施設で授業を行っています。
教えるということをあまりせず、生徒が自ら考え、話し合って答えを導き出すという授業です。
そしてこの教師は「先生の役割は教えることではない」と断言していました。
これはロジャーズも同様のことを言っていました。
ロジャーズは教師の役割を「学習促進者である」と説いたのです。
生徒が学習したいことが充分に学習できるようにサポートするのが役割だというのです。
そのために、教師は生徒の内面を常に理解している必要があるとも、説いていました。
また、引きこもりの支援者は、やはり援助される側の自主性を尊重していました。
決めるのは彼らであって、私が引っ張っていくのではないとも。
こちらもクライエントの主体性を尊重するロジャーズの臨床観と一致します。
また、この援助者は親と接触してから引きこもりの当事者と会えるまで、何年もかけて自宅に通い続けるようです。
部屋の扉越しに声をかけるのですが、決して無理はしません。
つまり、当事者が成長するのを気の遠くなるような時間をかけてサポートしていることになります。
ある意味、引きこもりの援助は、これしかないかもしれません。
ロジャーズがカウンセリングで重視したのは「経験」
その教育者、援助者に共通しているのは、答えやゴールにこだわっていない。
生徒やクライエントの「成長」にフォーカスしているところです。
ここも、ロジャーズの教育観、臨床観に通じます。
クライエントが成長することで、当人は様々な問題を解決し、困難を乗り越える。
カウンセリングがそのための経験の場の一つ。
そのため、カウンセリングと教育というのは密接に関連している要素が多いのです。
そうなると、結果ではなく過程を重視することになります。
教育にしても心理援助にしても、互いの関係性がどうなっているかという話になります。
そして、その関係性を決めるのは教師や援助者の言葉と態度です。
結果よりプロセス重視こそロジャーズのカウンセリング
ドキュメントされていた教師は、教室にいる生徒に投げかける言葉を慎重に選んでいました。
扉の向こうにいる無言の相手に対しても、援助者は発する言葉を一つ一つ厳密に選んでいました。
これらはまさにカウンセリング面接の場面そのものです。
ロジャーズのカウンセリングは関係性を築くために言葉の一つ一つを精査します。
投げかける言葉一つで、関係性が一変することもあるからです。
そして、どんな言葉を投げかけるかはクライエントが見えていなければ判断がつきません。
この場合の見えているというのは、視覚的なことだけを言っているわけではありません。
引きこもりの、扉の向こうにいる無言の相手に対しても同じことが言えます。
相手の内面がどれだけ把握できるかということです。
そしてカウンセラーがクライエントの内面をどれだけ把握出来ているかは、そのカウンセラーが発する言葉でわかります。
クライエントにしてみれば、カウンセラーが発する言葉によって、自分のことをどれだけ理解しているかがわかります。
そして、理解されればされるほど、クライエントは心が動いていくのです。
心が動けば新たな行動につながり、新しい経験につながります。
そうやって視野が広がり、捉え方の引き出しも増え、人間的な成長につながるから、クライエントは立ち直っていくことになります。
このプロセスについては、これまでメルマガで何度も触れてきたので、詳しくは割愛します。
結果より過程(プロセス)に集中する。
ロジャーズのカウンセリングの要点は、ここに極まっているといってもいいでしょう。
【動画】カール・ロジャーズの非指示的カウンセリングの実際
ロジャーズのカウンセリングの特徴の一つは「非指示的である」ということです。
アドバイスや説得、分析や解説・説明などをしない。
これが来談者中心療法の大きな特徴といえます。
ここからは動画での解説になります。
わかりやすく短時間で解説しましたので下の動画をご覧ください。
「臨床カウンセラー養成塾の無料メルマガ」でもっと読める!
こうした内容をもっと知りたいという方のために「臨床カウンセラー養成塾」のメルマガをお届けしています。あなたのスマホ、タブレット、PCに無料で読むことができます。ご購読をご希望される方は、下記からご登録頂けます。メールは「臨床カウンセラー養成塾」という件名で届きます。購読解除はメルマガの巻末(下部)より、いつでも出来ます。興味のある方はご購読ください。
追伸:
さらに、傾聴について、こうした皆が知らない真実を、今回一冊のレポート(56ページのPDF無料レポート)にまとめました。
無料PDFレポート「誤解されている傾聴スキル8つの真実」
~形だけの傾聴から、人と心通わす傾聴へ~
こういう話は、おそらく他では知り得ないと思います。
本当の意味で、現場で使える傾聴を身につけたい、そのために必要なことを知っておきたいという方。
下記フォームにお名前とメールアドレスを記入して「登録する」をクリックすると、PDFレポート(サポートメルマガつき)が届きますので、読んでみてください。
【無料PDFレポート「誤解されている傾聴スキル8つの真実」】
↓ ↓ ↓ ↓
【月額2980円のオンライン講座】
傾聴・カウンセリングや心理学、人生100年時代の幸せな生き方を学習できる「オンライン講座」が好評です。
会員限定サイトの動画セミナー、コラム記事が、スマホ・PC・タブレットから見放題でなんと月額2980円!









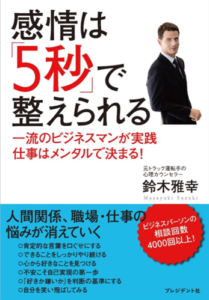
最近のコメント