パーソンセンタードアプローチとはカール・ロジャーズが来談者中心療法において、カウンセリングでカウンセラー(セラピスト)がクライエント(来談者)の悩みや問題ではなく人間性を中心に据える(大切にする)セラピーや教育といえます。
クライエントを一人の人間としてまっすぐに捉え、その人間性に接することに専念し、その人となりに関心を向け続ける。
パーソンセンタードアプローチは血の通ったコミュニケーションこそがクライエントの成長と変化、問題解決や精神機能の回復につながるとするもの。
その理論と実際を、以下にわかりやすくまとめました。
【筆者プロフィール】
心理カウンセラーとして6000件以上(2020年4月現在)のカウンセリングを実施。
5年間にわたりスクールカウンセラーとして教育現場の問題解決にあたり、現在も個別に教育相談を受ける。
大手一部上場企業を始めとした社員研修の講師として10年以上登壇し、臨床カウンセラー養成塾を10年以上運営。コーチとしても様々な目標達成に携わる。
著書「感情は5秒で整えられる(プレジデント社)」は台湾でも出版された。
詳しいプロフィールはこちら
もくじ
パーソンセンタードアプローチとは
「人間中心のセラピーこそ、成果が出る」
これはカール・R・ロジャーズが主張し、実践してきた概念です。
パーソンセンタード・アプローチとも呼ばれます。
私の師匠だった吉田哲が尊敬していた臨床家、遠藤勉氏も「人格主義カウンセリング」を唱えていました。
ただ、一言で「人間中心」とか「人格主義」といっても、それはどういうことなのか?
わかるようでわからないのではないでしょうか。
人間中心や人格主義を唱えた臨床家たちが言いたかったのは、クライエントを一人の人間として捉え、真っすぐ接することの大切さでした。
クライアントの抱えている問題や症状にではなく、クライエント自身の人間性にふれる努力をせよ。
クライアントの人となり、人生観、内面で躍動する感情、感覚、経験の世界。
こうしたものに着目し、共有し、その感覚をもってセラピーをする。
その方がはるかにセラピー効果も高いといいます。
その昔、九州大学で心療内科の礎を築いた池見酉次郎氏。
その池見氏は、病や臓器ではなく、患者を一人の人間として捉えることが大切と説いたといいます。
臨床を突き詰めると患者やクライエントへの接し方で重視すべきは同じ。
ところが、往々にして私たちカウンセラーはクライエントを病気や問題からしか捉えない。
それはクライエントを否定的に捉えていることと同じ。
ロジャーズが説いた「肯定的配慮」「積極的関心」からはずれてしまいます。
問題からしか捉えられないと、分析や解釈、問題視といった動き方をしたくなります。
病気からしか捉えられないと、診断、説明、説得といった動き方に偏ります。
カウンセリングの命、傾聴や共感的理解といった姿勢や態度が失われていきます。
病気や問題からしか捉えられないと、どうしても「治す」「解決する」というカウンセラー主導の働きかけになりがちです。
来談者中心療法カウンセリングの理論と実際
カウンセリンによるで問題解決や病気の治癒にはクライエントの人間的成長も重要な要素です。
薬物療法を続けてもクライエントの人間的成長がなければ予後が悪くなったり、治療が長期間にわたることもしばしばです。
人間中心というのは教育的な態度であり、クライエントの成長を信頼する姿勢です。
クライエントの内なる成長の可能性をカウンセラーが心から信じる。
そういう姿勢でクライエントの前に座り続けるからこそ、それがクライエントに伝わり、変化が起こり始めるわけです。
信頼が信頼を生み、確かな立ち直りが起こり、クライエントが人間として一段も二段も成長する。
この成長は永続的で、そうそう崩れることはありません。
クライエントの回復や問題解決に必要な人間的成長は、こうしたカウンセラーの姿勢や捉え方から生まれます。
カウンセラーが「そこが問題だ」「この症状をどうすれば」という解釈をするのではないんです。
「この人はこういう人間性で、こんな持ち味がある」とか、「そんな人生を歩んできたんだな」という感慨と実感です。
私の経験から言っても、このカウンセラーの感慨と実感が深くて確かなものであるからこそ、生きた応答が生まれるといえます。
クライエントを一人の人間として深く味わうことで生まれるカウンセラー側の感慨や実感。
これがクライエントに伝わるからこそ、クライエントは「理解された」という実感を持ちます。
こうした感慨や実感のないやり取りには、ぬくもりや絆を感じることは出来ません。
多くの臨床の現場で、こうした感慨や実感が失われたことで、カウンセラーは社会的な信用を失いました。
クライエントにまっすぐ接するためには、私たちカウンセラーが自分の人生をまっすぐ見る生き方が必要になります。
失われた信用を取り戻すには、カウンセラー一人一人が自分とまっすぐに向き合う生き方が求められます。
ロジャーズのセラピーの欠点
パーソンセンタードアプローチ(来談者中心療法)にも欠点はあります。
まず、カウンセラーの実力差によって、カウンセリングの成功率やクライエントが変化成長するまでの時間に、 バラつきや差が出ます。
他の心理療法はツールやワークなどを用いるため、そうしたバラつきや差が、来談者中心療法とくらべると大きくありません。
ただし、クライエントに対する信頼感と対話を重視する来談者中心療法は、心理的な深いコミュニケーションが可能となるので、クライエントの心理的な深い変化が起こりやすいと思います。
次に、 セラピーの様々な要素をクライエント主導で行うため、クライエント自身の問題意識、立ち直る力が弱い場合には、時間がかかったり、成功率が低くなるという欠点もあります。
また、統合失調症や双極性障害、内因性の強迫性障害やうつ病の場合、こうした精神病に直接的に改善効果をもたらす度合いは限定的です。
そもそも現代の精神医療では、こうした内因性の精神病を治癒させることはできず、寛解を一つのゴールにするのが限界です。
薬物療法によって症状を抑え、コントロールしながら、カウンセリングによって精神の安定を図り、生活環境などの調整を並行していくのが基本になります。
ただ、 一般に考えられている以上に、このパーソンセンタードアプローチ(来談者中心療法)はクライエントの精神機能の回復にかなりの効果をもたらすことも事実。
その成否を分ける大きなポイントが、人間中心の働きかけと人格主義に根ざした価値観と姿勢を有したカウンセラーの実力をや経験値、そして専門性となります。
今の日本に著しく欠けているのは、カウンセラーのこのような実力を引き上げるための適切な訓練・ トレーニングです。
また、そうした訓練を積極的に受けようと意識をもったカウンセラーが少ないことも、日本の社会でカウンセラーの信用が 落ちてしまった要因です。
【動画】カール・R・ロジャーズの来談者中心療法
最後に改めて「パーソンセンタードアプローチ(来談者中心療法)についてわかりやすく短い動画にまとめました。
パーソンセンタードアプローチとは何か?
なぜ来談者「中心」と言っているのか?
下記の短い動画でわかりやすく解説しています↓
上記の短い動画も「非常にわかりやすい」「納得できた」と好評ですので、ぜひご覧ください↑
無料PDFレポート「誤解されている傾聴スキル8つの真実」
傾聴・カウンセリングについて、こうした皆が知らない真実を、今回一冊のレポート(56ページのPDF無料レポート)にまとめました。
無料PDFレポート「誤解されている傾聴スキル8つの真実」
~形だけの傾聴から、人と心通わす傾聴へ~こういう話は、おそらく他では知り得ないと思います。
本当の意味で、現場で使える傾聴を身につけたい、そのために必要なことを知っておきたいという方。
下記「無料PDFレポート」をクリックすると、PDFレポート(サポートメルマガつき)が届きますので、読んでみてください。
「臨床カウンセラー養成塾の無料メルマガ」でもっと読める!
こうした内容をもっと知りたいという方のために「臨床カウンセラー養成塾」のメルマガをお届けしています。あなたのスマホ、タブレット、PCに無料で読むことができます。ご購読をご希望される方は、下記からご登録頂けます。メールは「臨床カウンセラー養成塾」という件名で届きます。購読解除はメルマガの巻末(下部)より、いつでも出来ます。興味のある方はご購読ください。
【月額2980円のオンライン講座】
傾聴・カウンセリングや心理学、人生100年時代の幸せな生き方を学習できる「オンライン講座」が好評です。
会員限定サイトの動画セミナー、コラム記事が、スマホ・PC・タブレットから見放題でなんと月額2980円!











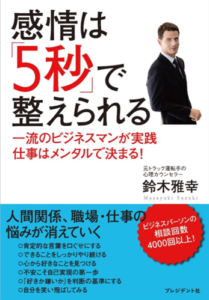
最近のコメント