傾聴の訓練、トレーニングの方法は、ほとんどの学習機関で意味のない、実践で通用しない内容が行われています。
心理、教育、医療、福祉、ビジネスなど、様々な現場で活用できる傾聴力をマスターするには、正しいトレーニングの方法が必要です。
以下に、その方法について具体的にお伝えします。
もくじ
傾聴は言葉の繰り返しなどではない
「オウム返しをしたら、クライエントに怒られました」
このお話は本当に多くの方から聞くお話です。
また、養成塾のロールプレイ講座でも、よく見られる光景です。
つまり、相手が話したら、それをオウム返しする。
続けて話したら、またオウム返しする。ずっとオウム返しする・・・・・
これでは、話し手がウンザリするのも無理はありません(笑)
いえ、笑いごとではないんです。
これを実際のカウンセリングや相談面接でもしているわけですから。
どういうわけか「カウンセリングではオウム返し?」という教えが日本ではかなり浸透してしまっているようです。
でも、考えてみてください。
あなたも普段の会話で、相手の言葉をオウム返しし続ける・・・などという対応をしていますか?
そんなことばかりやっていたら「バカにしてんの?」って言われると思いませんか?
それなのに、カウンセリングでは、このオウム返しを頻繁にやるようになぜかまことしやかに教えられているのです。
もちろんカウンセリングは、日常会話よりもっとデリケートで、はるかに細やかな神経と高度なスキルが求められます。
そんな状況でオウム返しを続けたらどういうことになるでしょう。
もちろん、オウム返しが全てダメだとはいいません。
むしろ「こういう場面こそオウム返しが生きる」という場面があります。
要はその時その時に最も適切だという対応ができればいいわけです。
オウム返しを頼りにするしかない学習やセラピストたち。
彼らには、ある背景が存在します。
それは「クライエントの話にどんな言葉を返せばいいのかわからない」という戸惑いです。
ですからカウンセリング学習で習得すべきは、様々な場面へどんな言葉や態度で対応するか、適切な対応ができる力です。
この対応力を身につければ、カウンセラーとしての土台ができ、カウンセリングの本当の素晴らしさ、奥深さを肌で実感できるようになります。
面接での瞬間的な反射神経を磨くことで、様々な場面に対応できる「聞き手」を目指します。
正しい傾聴スキル研修、トレーニングとは
「良いロールプレイの選び方ってありますか?」
傾聴訓練(トレーニング)の一方法として、ロールプレイというものがあります。
互いに話し手と聞き手になって、会話のやり取りや実際のカウンセリングのようなやり取りを行います。
そこで、本当に訓練になるロールプレイと、訓練効果の薄いロールプレイの見分け方をご紹介します。
本当に訓練になるロールプレイにするには、下記がポイントになります。
1)録音を撮る
会話のやり取りを録音し、その音声記録を聴き返します。
人間の記憶はとても曖昧なので、正確に振り返るためには、こうした記録を元に検討する必要があります。
2)本当の話をする
作り話や作られた役を演じるようでは、茶番になってしまいます。
悩んでいることではなくても、興味のあること、考えていることなど、本当の話をもとにロールプレイを行う必要があります。
3)一言半句のレベルで会話を解析していく
録音を聴きながら、一言一言をきっちり検証していきます。
なぜなら、カウンセリングはたった一言が重要な場面があるからです。
また、一言でも聞き漏らしたら、カウンセリングはしっかりとはできません。
4)一言半句のレベルで指導できる指導者に学ぶ
生徒だけでロールプレイをやっても、あまり進歩は見込めません。
きちんと指導できる力を持った指導者に指導を仰げることが前提です。
生徒が聞けないものを聞き取れる力を持った指導者がベストです。
5)時間をあらかじめ決める
際限なくやってしまうと、時には危険なことがあります。
特に心理的な、内面的な話の場合は要注意です。
また、ロールプレイで話した内容は、授業が終わった後などで、喫茶店などで続けることは控えるほうが賢明です。
こうのようなポイントをおさえたロールプレイを行えば、実践的な傾聴の力が徐々に身についていきます。
傾聴力を鍛えるには
「一度身についたものは忘れない」
カウンセリングの研修、講座などでは、塾生が「聞けるようになる」ために授業を受けています。
クライエントの話を細部にわたり正確に聞ける。
その理解も的確であり、深いものを伴っている。
更には適切な応答の選択ができ、配慮にも富んでいる。
この3拍子が揃って初めてしっかりとしたカウンセリングになります。
しかし、初めからこのような聞き方、理解の仕方ができるわけではありません。
最初はもちろん、相当に苦労しますし、実際に苦戦します。
できるだけ正確に聞こうと思っても、余計な感情や思い込みが邪魔したり、集中力がなかなか持続しなかったりして聞けません。
しかし、それでも聞くための努力を続けていくうちに、やがてある時「聞けるようになっている自分」に気づきます。
そしてこうした力というのは、一旦定着してしまうと、そうそう簡単には衰えることはありません。
そう、一旦身についたものは、忘れなくなるわけです。
ですから、ブランクがある程度空いても、程なくして戻せます。
これは「スポーツの上達」の概念と変わりません。
スポーツの技量でも、一定のレベルに達するまでには、多くの時間と労力を必要とします。
しかし、一旦身につき、それが定着してしまえば、余程のことが起きない限り、これも忘れなくなるものです。
いわゆる「身体が覚えてしまう」というやつですね。
カウンセリングに話を戻します。
聞く力を身につけるまでは、いくら聞こうと意識しても聞けない。
意識的にいくら努力して聞こうとしても、それでも思うように聞けないわけです。
ところが、その一線を越えて聞けるようになってしまうと、敢えて聞こうという意識を持たなくても、自然と聞けてしまう。
それなりに集中状態を作り出せれば、自ずと聞けるようになるんです。
修練を積むと、こういう変化が起きるわけですね。
大切なのかは、そのレベルにまで到達してしまうことなんです。
到達してしまえば、今までとは違う景色が見え、違う感覚が働きます。
ですから、適切な訓練や努力を続けていくことで、とにかくそのレベルまで到達してしまうことが大切です。
そうした神経が意識せずとも働いてくれるのです。
つまり、反射神経として身につけてしまえ・・ということですね。
無料PDFレポート「誤解されている傾聴スキル8つの真実」
傾聴・カウンセリングについて、こうした皆が知らない真実を、今回一冊のレポート(56ページのPDF無料レポート)にまとめました。
無料PDFレポート「誤解されている傾聴スキル8つの真実」
~形だけの傾聴から、人と心通わす傾聴へ~こういう話は、おそらく他では知り得ないと思います。
本当の意味で、現場で使える傾聴を身につけたい、そのために必要なことを知っておきたいという方。
下記「無料PDFレポート」をクリックすると、PDFレポート(サポートメルマガつき)が届きますので、読んでみてください。
「臨床カウンセラー養成塾の無料メルマガ」でもっと読める!
こうした内容をもっと知りたいという方のために「臨床カウンセラー養成塾」のメルマガをお届けしています。あなたのスマホ、タブレット、PCに無料で読むことができます。ご購読をご希望される方は、下記からご登録頂けます。メールは「臨床カウンセラー養成塾」という件名で届きます。購読解除はメルマガの巻末(下部)より、いつでも出来ます。興味のある方はご購読ください。
【月額2980円のオンライン講座】
傾聴・カウンセリングや心理学、人生100年時代の幸せな生き方を学習できる「オンライン講座」が好評です。
会員限定サイトの動画セミナー、コラム記事が、スマホ・PC・タブレットから見放題でなんと月額2980円!


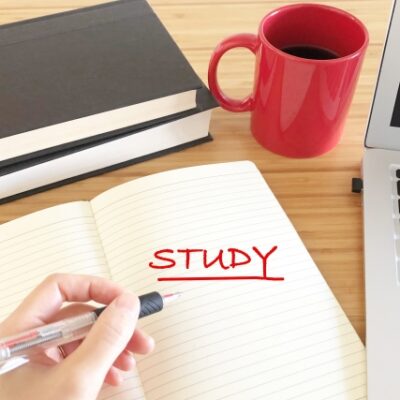







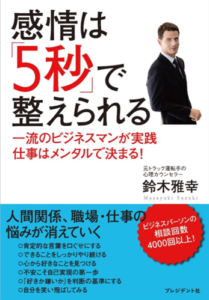
最近のコメント