傾聴とは、実は観察手段の一つであり、相手の話を聞いて即、いかに適切な言葉で応じるかがポイントです。
そして、傾聴やカウンセリングの力をつけるのと、スポーツの上達とは、実は同じなんです。
こんなに大切な話を誰も書いていませんので、今回、詳しく書いてみました。
もくじ
聞く力(傾聴力)の本当の意味
聞く力という表現があります。
養成塾に来られる人の多くが、この聞く力をつけたい、ちゃんと聞けるようになりたいと言います。
では、この聞く力とは、どんな力のことをいうのでしょうか。
聞く力のある人は、コミュニケーションがとても上手です。
だから人間関係で楽しい思いをすることが多くなります。
相手と話がかみ合いますし、話が盛り上がったり深まったりします。
また、聞く力のある人は会話が上手なだけでなく、人付き合いそのものも上手です。
相手の心理や場の状況をしっかりと把握できるので、それに適した言動や態度が取れるからです。
なおかつ、自分自身の心理に対しても、リアルタイムで把握(意識)できるので、言葉や態度の選択にブレがないのです。
傾聴とは観察手段の一つ
つまり、聞く力というのはすなはち「観察力」なんです。
ここでいう「観察力」とは視覚的なことだけでなく、聴覚も含めて、インプットが正確であるという意味です。
正確に観察、そして把握する力があるということになります。
例えば、自分の話したいことばかりを、相手や状況を考えずに、延々と話し続ける。
相手の気持ちを押しはかることなく、自分の考えや推測だけで動く。
これは、相手や相手との関係性、そして場の状況を正確にインプット出来ていないことで起こることです。
つまり聞く力が必要になるということ。
聞く力をつけることが、こうした問題解決に一番だということになります。
では、どうすれば聞く力をつけることが出来るのでしょうか。
傾聴・聞くことを邪魔するものとは?
聞く力とは観察力だとお伝えしました。
この観察力を邪魔するものを解消することが解決のカギを握るんです。
相手の心理や相手との関係性、場の状況、そして自分の心理を観る目を曇らすものですね。
この正体を突き止め、曇りのない目を通して観察が出来れば、自ずと物事を正確に観察することができます。
目を曇らすものは、いろいろあります。
自分の思い込みであったり、過去の経験から染み付いた捉え方だったり、好き嫌いという感情であったり・・・・
そこから生まれる怖れ、怒り、嫌悪、不安、失望などが生じると、物事を正確に観ることを妨げます。
こうなると私たちは、物事を自分の見たいように見ようとするし、聞きたいように聞こうとします。
目の前で起きている事を正確にインプット出来ないため、仕事が上手くいかなかったり、人間関係で躓いたりしてしまうのです。
こうした邪魔する現象が起きないようにするために必要なことは、邪魔する要素に気づくことと、正確にインプットする術を身につけることです。
そういう意味で私が言う聞く力をつけるというのは、そうした人間の総合的な力を磨くということなのです。
そのためには、自分がどういうインプットの仕方を(無意識に)してしまっているかを知ることが一番効果的です。
自分のしてしまっていることからスタートするのが、聞く力をつける最短コースであり、最も確かな方法なんですね。
「現場から学ぶ」これが対応力を磨く王道
「事件は会議室で起きているんじゃない。現場で起きているんだ!」
「踊る大走査線」という映画での有名なセリフです。
織田裕二演じる主人公の刑事が、警察幹部に向かってたたきつける言葉。
これ、いろいろな分野で言えることではないかなと思うんです。
カウンセリングも全く同じ。
カウンセリングや相談内容となる問題って、教室やセミナールーム、ましてテキストの上で起きるものではないですよね。
相談室や教育現場、そしてクライエントの日々の生活、まさに「現場」で日々起きるもの。
だからこそ、その現場から出発する学習が必須です。
逐語検討や事例検討などを通して、常に現場で起きていることから学ぶ。
なぜなら、現場は常に「いざ」や「さあどうしよう?」の連続だからです。
現場で必要なのは知識や理論だけではなく「返す言葉を見つける力」応答力
心理学の理論や知識だけでは、様々な問題にぶつかる現場にて、カウンセラーは常に「いざ」に即座に対応していかなければなりません。
そこに必要なのは既存の知識でも定型化した手法やスキルでもなく、即応できる「反射神経」です。
カウンセリングの学習で、全ての人が一番困ることって何だと思いますか?
知識不足?理論の理解?
いえ、そんなことじゃないんです。
知識も理論も必要ですが、実際の現場でものすごく困ることが出てくるんです。
では、その「ものすごく困ること」とは何か?
答えは「返す言葉が見つからない」ってことなんです。
何を知っているか?ではなく「実際に何をしてしまっているか?」が重要
クライエントがいろいろな話をされますよね。
それに対して聞いているカウンセラーがどんな言葉を返せば良いのか?
そこの場面でみんなが困っているんです。
つまり、面接の中で「適切な応答が浮かばない」という場面です。
資格保持者も、プロの方も例外ではありません。
なぜ、そうなってしまうのか?
それは、カウンセリングの勉強が、理論などの知識に偏っているのが原因です。
また、実践のスキル訓練も現実離れした人工的な内容に終始しているからです。
ロールプレイ一つとっても、録音すらとらず、参加者の記憶だけで「良かった」「悪かった」と言って終わっているからです。
「基本はオウム返しだ」「もっと情感を込めて」といった実践に全く活用できないアドバイスによって、カウンセリングの学習は混乱しています。
では、どのような学習方法、トレーニング法が良いのか?
・やり取りを録音し、逐語にして一言半句のレベルで正確に振り返る。
・実際の逐語記録を様々な角度から検討する。
そうした「具体的な素材」で学習してはじめてカウンセリングのスキルは向上します。
「何を知っているか?」ではなく「実際に何をやってしまっているのか?」
ここを正確に振り返り、改善を重ねていくこと。
本当はここから出発するしかないわけです。
カウンセリングの上達はスポーツの技能習得と同じだった
カウンセリングの技術習得は、スポーツと一緒です。
野球が上手くなるには、本を読んで野球の知識や理論を覚えただけでは上手くならないですよね。
実際に練習をして、打ち方や投げ方など、自分の身体の使い方をチェックしてもらう。
試合をして、その動き方などを振り返って改善していく。
そういうことをやっていますよね。
カウンセリングも全く同じです。
自分が面接で実際にやっていることを検討し、次に活かす。
そこで聞き方のクセ、反応の仕方のクセ、実際にどう対応しているのか?
ここから出発すること。
それがカウンセリングの実践に絶対に必要なことなのです。
野球の打者が、全て違う相手投手の一級一級に対し、どうすれば良かったかを検討しますよね。
それと同じようにカウンセリングでもクライエントの一言一言にカウンセラーがどんな言葉で応じれば良かったを検討するしかありません。
なぜなら、そのカウンセラーのたった一言によって、面接の流れは大きく変わってしまうから。
カウンセリングの成否が、カウンセラーの一言によって決まってくるからです。
傾聴やカウンセリングを学ぶ際に、あなたはそんなことを考えたことがあるでしょうか?
実際に臨床の現場では、こうしたカウンセラーの一言が決め手になっています。
「臨床カウンセラー養成塾の無料メルマガ」でもっと読める!
こうした内容をもっと知りたいという方のために「臨床カウンセラー養成塾」のメルマガをお届けしています。あなたのスマホ、タブレット、PCに無料で読むことができます。ご購読をご希望される方は、下記からご登録頂けます。メールは「臨床カウンセラー養成塾」という件名で届きます。購読解除はメルマガの巻末(下部)より、いつでも出来ます。興味のある方はご購読ください。
追伸:
さらに、傾聴について、こうした皆が知らない真実を、今回一冊のレポート(56ページのPDF無料レポート)にまとめました。
無料PDFレポート「誤解されている傾聴スキル8つの真実」
~形だけの傾聴から、人と心通わす傾聴へ~
こういう話は、おそらく他では知り得ないと思います。
本当の意味で、現場で使える傾聴を身につけたい、そのために必要なことを知っておきたいという方。
下記フォームにお名前とメールアドレスを記入して「登録する」をクリックすると、PDFレポート(サポートメルマガつき)が届きますので、読んでみてください。
【無料PDFレポート「誤解されている傾聴スキル8つの真実」】
↓ ↓ ↓ ↓
【月額2980円のオンライン講座】
傾聴・カウンセリングや心理学、人生100年時代の幸せな生き方を学習できる「オンライン講座」が好評です。
会員限定サイトの動画セミナー、コラム記事が、スマホ・PC・タブレットから見放題でなんと月額2980円!













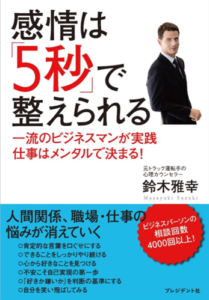
最近のコメント