カウンセリングを受けると人が立ち直れるのは、その人の心が動かされるからです。
知識や情報を得ても解決しない問題は心理的問題になります。
心理的問題が解決するには、何らかの心理状態が変化する必要があります。
カウンセリングでは、そうした心理状態の変化を「人間的な成長によって起こるもの」とし、その成長を呼び起こします。
以下にわかりやすく解説しました。
もくじ
立ち直るのは「成長」があるから
私はカウンセリングの個別レッスン、傾聴スキルセミナーやグループレッスン、
そしてカウンセリング講座を行っています。
こうした学習の本来の目指すところは、受講者の「成長」です。
何らかの情報や知識を得るだけなら簡単な話です。
しかし、それを自分のものにしていくには、受講者自身の成長が必要です。
ですから、継続的な受講を通して受講者の方々の成長が観られたことは、私としても嬉しいところです。
そして、成長した証といえるのが、具体的な行動の変化です。
手を挙げなかった人が手を挙げてロールプレイに参加した。
応答の精度が見るからに高くなった。
発言する時に選ぶ言葉や表現が変わった。
表情や顔つきにはっきりとした変化が現れた。
こうした具体的な変化が、その人の人間的な成長をあらわしています。
そしてこれは教育の本来の目的だと思います。
わかりやすくいうと、教育の本質は「人柄を育てること」だと思っています。
より思慮深くなった。
より忍耐強く(あきらめなく)なった。
より積極的になった。
より愛情深くなった。
より寛容になった。
より理性的になった。
より視野を広くもてるようになった。
これが成長であり「人柄が育つ」ことです。
そう、何も難しい理論など必要なく、シンプルに言えてしまうことです。
人柄が育てば、能力やスキルは後からついてくるところがあります。
ただ、その成長には時間が必要だということ。
どうしても試行錯誤や一進一退などを経験するということ。
ここに”難しさ”があります。
カウンセリングは成長のための経験の場
そして、レッスンの中でもお伝えしましたが、人が成長するためには時間が必要であり、しかも「必要な時間がある」ということ。
その人にとっての必要な時間ですね。
その時間は人によって違います。
数日で成長する人もいれば、数年単位の時間が必要な人もいます。
それは比較して早い、遅いという話ではありません。
早ければいいという話でもありません。
「その人にとって必要な時間がある」ということです。
Aさんは数日で成長出来た。
でも、Bさんは5年かかった。
それはBさんにとって5年という時間が必要だったということです。
でも、本当に成長が出来たとき、Bさんは5年を長いと思うのではなく、必要な5年だったと思えるでしょう。
そして5年の「重み」を大切にしながら、その後の人生を生きていくことができるでしょう。
カウンセリングというのは、こうした成長のための経験の一つです。
カウンセリングによって、クライエントは人生にとって必要な人間的成長を経験します。
ですから、そこに寄り添うカウンセラーは「人間的な成長とは何か」ということをよくよく熟知している必要があります。
カウンセラーなりに人生観、人間観、そして教育観(成長観)といったものが必要です。
こうした哲学を経験から築いていけないと、カウンセリングそのものが浅いものになります。
カウンセリングは人間的成長(教育)の機会でもある
人生で悩むとき、私たちは時には物事を深く捉えることが必要になります。
視点を高くしたり、拡げたり、角度を変えたりしながら、自分というものや自分の人生を捉え直す。
その時、それまで以上に人生を、そして生きるということをさらに深く捉え、理解する必要が出てきます。
それはまさに教育そのものです。
困難に直面したり、挫折を経験するということは、まさに教育を経験していることでもあるのです。
困難や周囲の出来事、縁のある人間関係から教わり、自分の人間性を育てていく。
まさに「教わり」そして「育てる」ですから「教育」なわけです。
カウンセリングは受けることもまた教育となり、それを提供することも教育になり、そのカウンセリングを学ぶということもまた「教育である」といえますね。
カウンセラーはクライエントの心が動く応答を投げかける
カウンセラーが「心ある応答」を投げ返せば、クライエントの心が動く。
この場合の心が動くとは、ハッとするとか腑に落ちるとか、共感してもらえたという実感などから、小さな感動を覚えることです。
そうした心の動きが起きるからこそ、クライエントの精神機能が回復し、立ち直っていけるわけです。
そして、そのようにクライエントの心を動かすものは、知的な働きかけではありません。
それは情緒的な交流であり、カウンセラーの心からの応答です。
そして、それが心からの確かな応答であるとクライエント自身が実感することです。
そうした心の交流があって、初めてクライエントは立ち直っていく。
決して情報提供や助言や分析、説得ではなく、ましてカウンセラーの価値観を押しつけることでもないのです。
そんな講義をした後に、受講者から次のような質問がありました。
カウンセラーも自然と心動かされることで共感的理解に通じる
クライエントの心が動くということはとても重要だと、今のお話を聞いて感じました。
その時、カウンセラーの心の動きも重要だと思うのですが、その場合、カウンセラーは心を「動かす」必要があるのでしょうか?
それとも「動いていく」ものなのでしょうか?
これは非常に鋭い、良い質問でしたので、私は率直に答えました。
結論からいうと、心というものは動かせるものではありません。
動かすというよりも「動かされる」といえるでしょう。
私の師匠であった吉田は「もっと心を動かさないと」と表現していました。
しかしその真意はこういうことです。
カウンセラーはクライエントの話を、とにかく興味津々に聞き続ける。
これをしているとカウンセラーはクライエントの話にものすごく集中していきます。
クライエントの話に対して、鋭くて深い集中力が生まれるわけです。
そうなると、カウンセラーの中で、クライエントが経験したことがありありと映像化されてきます。
このイメージが鮮明であればあるほど、カウンセラーの心は動いてきます。
つまり、心だけを意識的に動かそうとするのではなく、クライエントの経験に没頭していく過程で、心が動いていくのです。
これは感情的になるということとは違います。
あくまでも理性的にしっかりと話を聞き、そこから生まれる鮮明な理解によって生まれる心の動きです。
実際にはもう少し具体例なども交えて、細かく説明しました。
質問した受講生は納得できたようでした。
心が動かないで悩むカウンセラー
多くのカウンセラーやカウンセリング学習者がぶつかる壁は、ここなのです。
つまり、クライエントの話を聞いても、心が動かないのです。
心が動かないので、知的な働きが優先して余計なことを言ったり、ピントのずれた応答になってしまう。
はたまた感情的になってしまう(これを心理の世界で逆転移といったりします)。
逆にクライエントの話を鮮明にイメージでき、そこから心が動いていくこと、これを別な言葉でいうと共感的理解といいます。
クライエントの気持ちを実感をもって理解できるので、その実感がそのまま言葉になれば、適切な応答になります。
多くのカウンセラーやカウンセリング学習者が、こうした心の動きが起きずに苦労しているといってもいいでしょう。
人間が心動かされるのは、その対象に強く深い関心を持った時です。
クライエントの話、クライエントの人間性、そしてクライエントの人生に強く深い関心が向く。
そうなると、カウンセリングは確かな道を辿ることができるのです。
その具体的な方法やトレーニングを養成塾や個別レッスンでは行っています。
「臨床カウンセラー養成塾の無料メルマガ」でもっと読める!
こうした内容をもっと知りたいという方のために「臨床カウンセラー養成塾」のメルマガをお届けしています。あなたのスマホ、タブレット、PCに無料で読むことができます。ご購読をご希望される方は、下記からご登録頂けます。メールは「臨床カウンセラー養成塾」という件名で届きます。購読解除はメルマガの巻末(下部)より、いつでも出来ます。興味のある方はご購読ください。
追伸:
さらに、傾聴について、こうした皆が知らない真実を、今回一冊のレポート(56ページのPDF無料レポート)にまとめました。
無料PDFレポート「誤解されている傾聴スキル8つの真実」
~形だけの傾聴から、人と心通わす傾聴へ~
こういう話は、おそらく他では知り得ないと思います。
本当の意味で、現場で使える傾聴を身につけたい、そのために必要なことを知っておきたいという方。
下記フォームにお名前とメールアドレスを記入して「登録する」をクリックすると、PDFレポート(サポートメルマガつき)が届きますので、読んでみてください。
【無料PDFレポート「誤解されている傾聴スキル8つの真実」】
↓ ↓ ↓ ↓
【月額2980円のオンライン講座】
傾聴・カウンセリングや心理学、人生100年時代の幸せな生き方を学習できる「オンライン講座」が好評です。
会員限定サイトの動画セミナー、コラム記事が、スマホ・PC・タブレットから見放題でなんと月額2980円!









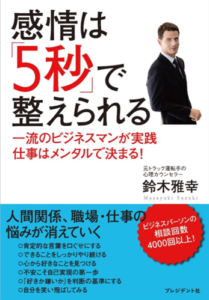
最近のコメント